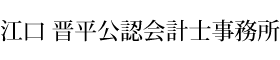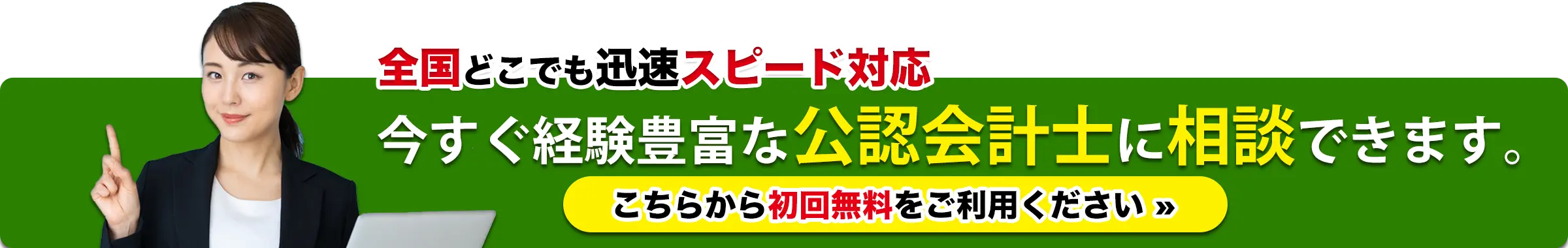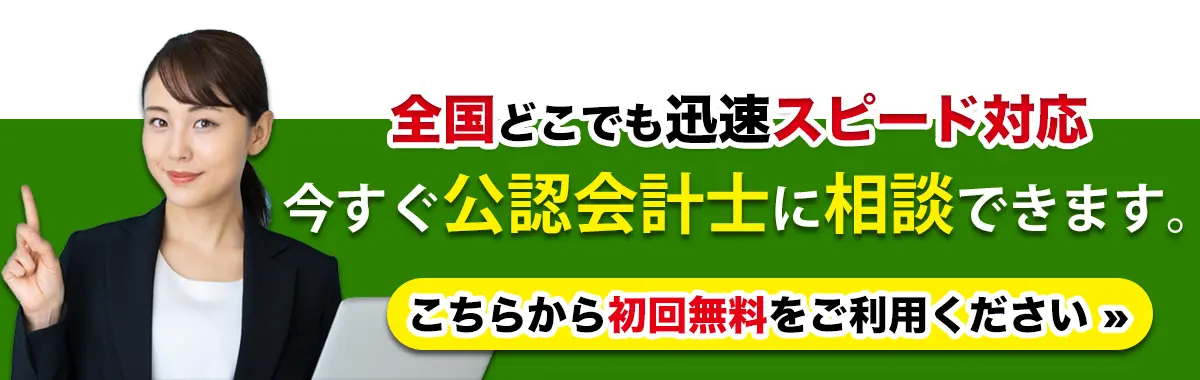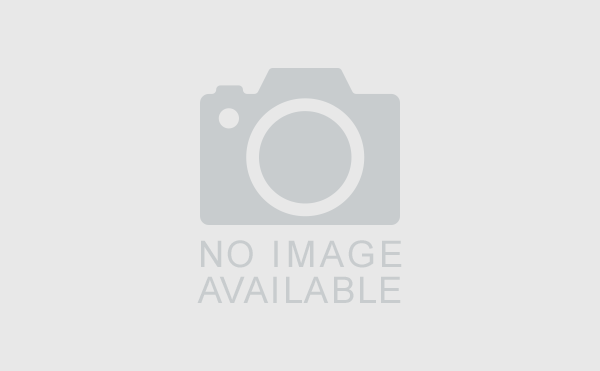AUP契約書とは?
AUP(Agreed Upon Procedures:合意された手続)契約書とは、依頼者と公認会計士が「どの範囲で、どの手続を実施するのか」を事前に合意し、文書として取り交わすものです。
監査契約書と異なり、AUP契約書には「保証意見を表明する」という内容は含まれません。あくまで「依頼者が希望する限定的な手続を実施し、その事実を報告する」ことに重点が置かれます。
例えば「売上取引の一部に不正がないか確認したい」「補助金申請の対象となる費用が正しく処理されているか確認したい」といった依頼に応じて、その範囲を契約書で明確に規定します。これにより依頼者と会計士の間で期待のズレが生じにくくなり、後のトラブル防止にもつながります。
AUP契約書が必要な理由
AUP契約書を交わすことには大きな意義があります。
- 手続の範囲を明確にできるため、会計士と依頼者の認識が一致する。
- 実施内容を契約上で限定することで、会計士の責任範囲を適切に区切れる。
- 依頼者は「必要な部分だけ」を効率的に調査でき、無駄なコストを避けられる。
- 報告書の利用者に対して、契約上の範囲を説明できる。
特にAUPは「保証を伴わない」業務であるため、契約書にその点を明記しておくことが不可欠です。
AUP契約書に含めるべき主要項目
AUP契約書を作成する際には、以下の項目を明記することが基本です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 業務の目的 | なぜこのAUPを依頼するのか(例:補助金申請のため、投資判断のため)。 |
| 業務の範囲 | どの勘定科目や取引を対象にするのかを限定的に記載。 |
| 実施する手続 | 具体的にどのような検証・確認を行うかを列挙。 |
| 報告の形式 | 事実を記載するのみで保証意見は含まないことを明記。 |
| 責任の範囲 | 会計士は契約上合意された手続以外の責任を負わない旨を明記。 |
| 契約期間 | いつまでに実施・報告するかの期限を設定。 |
| 報酬 | 業務の対価と支払い条件。 |
AUP契約書モデル(サンプル条項)
以下はAUP契約書に盛り込む典型的な条項例です。実際の契約書では弁護士・会計士の確認を経ることをおすすめします。
- 第1条(目的):本契約は、依頼者の依頼に基づき、公認会計士が合意された手続を実施し、その結果を報告することを目的とする。
- 第2条(業務範囲):会計士は、依頼者と合意した以下の取引についてのみ手続を実施する。…
- 第3条(実施手続):会計士は、取引記録の突合、残高確認、証憑調査など、依頼者と合意した方法に従って業務を実施する。
- 第4条(報告):会計士は、実施した手続とその結果を事実として報告する。保証意見を表明しないことを明記する。
- 第5条(責任):会計士の責任は、本契約に定める手続の実施範囲に限定される。
- 第6条(契約期間):本契約は〇年〇月〇日から〇年〇月〇日まで有効とする。
- 第7条(報酬):依頼者は、会計士に対し本業務に係る報酬〇〇円を支払う。
AUP契約書作成時の注意点
AUP契約書を作成する際に特に注意すべき点は以下の通りです。
- 保証を伴わないことを明確に記載する:依頼者や第三者が「監査報告書と同じ」と誤解しないようにする必要があります。
- 範囲を具体的に記載する:「売上の確認」ではなく「2024年4月~6月の売上取引のうち主要取引先3社分」といったように、対象を具体的に限定します。
- 報告書の利用者を明記する:依頼者だけが利用するのか、金融機関など外部も利用するのかを明らかにします。
- 契約期間と報酬条件を明確にする:短期間で完了できるのがAUPの特徴なので、スケジュール感を契約に落とし込むことが重要です。
AUP契約書が活用される具体的なシーン
AUP契約書は実務上、以下のようなシーンで活用されます。
- M&Aのデューデリジェンスにおいて、対象会社の売上や在庫を限定的に確認する場合。
- 金融機関が融資判断を行う際に、担保資産や特定の取引を確認する場合。
- 補助金や助成金の申請において、支出の一部を検証する場合。
- 子会社や関連会社の特定勘定科目を本社が確認する場合。
このようにAUP契約書は「必要な部分だけを確認したい」というニーズに応えるツールとして幅広く活用されています。
AUP契約書は依頼内容を明確にするための必須ツール
AUP契約書は、監査契約書とは異なり「保証を伴わず、限定的な調査を行う」ための文書です。契約書を交わすことで依頼者と会計士の間で期待値のズレを防ぎ、実務をスムーズに進められます。
作成にあたっては、業務の目的・範囲・手続内容・責任範囲を明記し、保証を行わないことを明確に示すことが重要です。
当サイトでは、AUPと監査の違いについても詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。