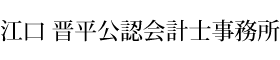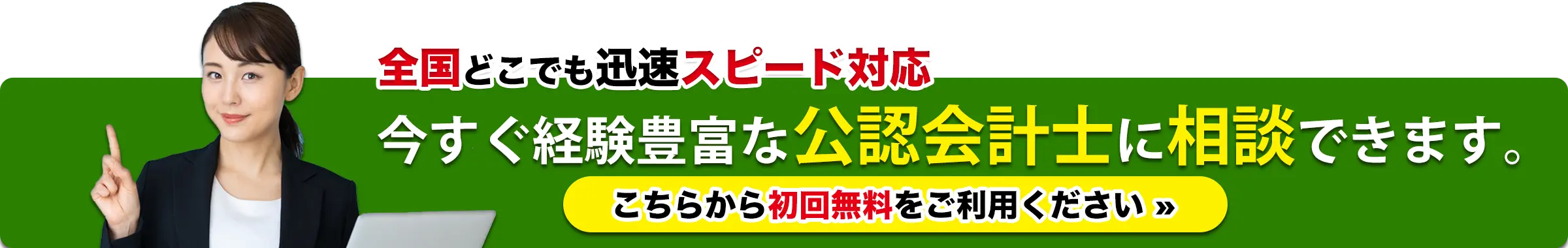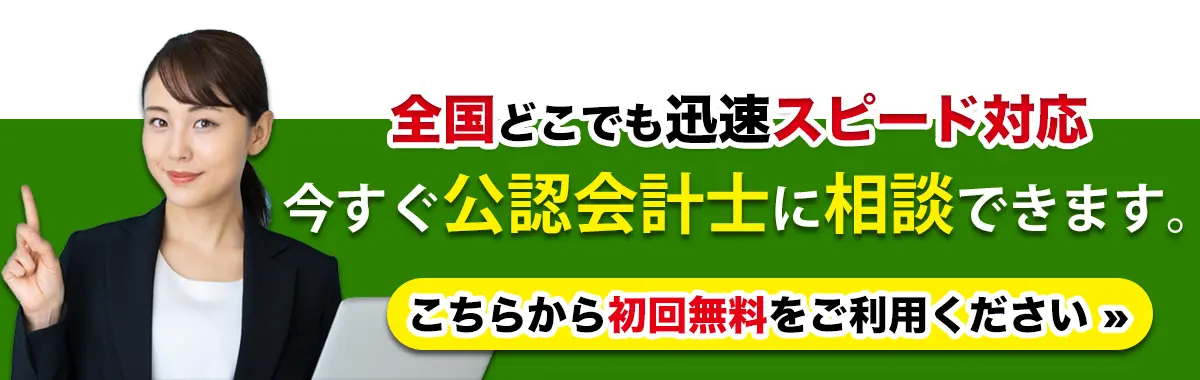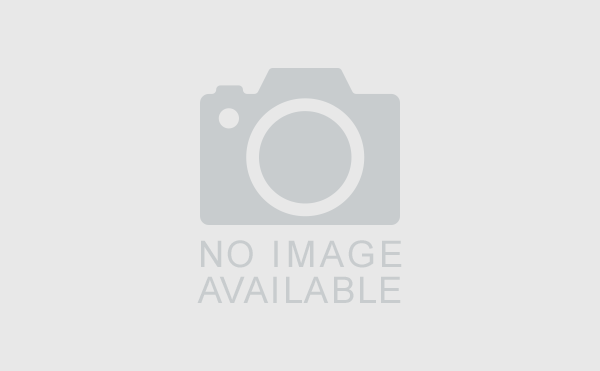派遣事業の更新審査では、資産要件や責任者体制、教育訓練と並んで「雇用安定措置」が必ずチェックされます。
労働者派遣法に基づき、派遣元事業主は一定の条件を満たす派遣労働者に対して「直接雇用依頼」や「就業機会の確保」といった雇用安定措置を講じる義務があります。
この雇用安定措置が適切に実施されていないと、労働局からの是正勧告や更新不許可につながる可能性があります。この記事では、派遣事業更新に必要な雇用安定措置の基本と実務対応、不許可リスクを避けるためのポイントを整理しました。
雇用安定措置が更新審査で重要な理由
雇用安定措置は、派遣労働者が不安定な雇用状態に陥らないよう保護するための仕組みです。
とくに「3年ルール」により、同一の派遣労働者が同一の派遣先で継続して働ける期間には制限があり、派遣元はこの時点で直接雇用の依頼や他の就業機会の確保を行う必要があります。
この義務を怠ると、派遣労働者のキャリア形成を軽視しているとみなされ、派遣事業更新の不許可事例と回避方法にもあるように不許可の典型要因となります。
雇用安定措置の基本要件
派遣元が講じるべき雇用安定措置には次の2つがあります。
- 直接雇用依頼
3年の派遣期間が満了する前に、派遣先に対して労働者を直接雇用するよう依頼すること。 - 就業機会確保措置
派遣先が直接雇用を拒否した場合、新たな派遣先の提供や教育訓練などを実施すること。
これらは「形式的にやればよい」というものではなく、文書で記録を残し、労働局に説明できる体制を整えておくことが不可欠です。
👉 関連:派遣事業更新に必要な教育訓練体制ガイド
直接雇用依頼の流れと実務対応
直接雇用依頼は以下の手順で行うのが望ましいとされています。
- 派遣期間満了の半年前を目安に準備
更新スケジュール管理と連動して動き出すことが大切です。 - 派遣先への依頼
書面(依頼書やメール)で直接雇用の依頼を行い、記録を保存します。 - 派遣労働者への説明
依頼を行った事実と結果を労働者に伝え、今後のキャリア形成について話し合います。 - 拒否された場合の対応
派遣先が拒否した場合には、次に説明する「就業機会確保措置」に進みます。
👉 関連:派遣事業更新スケジュール管理
就業機会確保措置の実務ポイント
派遣先が直接雇用を拒否した場合、派遣元は以下のような就業機会確保措置を講じなければなりません。
- 新たな派遣先の紹介
- キャリア支援のための教育訓練
- 職業紹介(有料職業紹介事業を兼営する場合)
重要なのは「実施した証拠」を残すことです。紹介状のコピー、研修受講記録、面談記録などを保存しておけば、労働局からの指摘に対しても根拠を示せます。
雇用安定措置に関する不許可リスク事例
典型的な不許可リスクは以下のようなものです。
- 直接雇用依頼をしていない
- 就業機会確保措置を講じていない
- 実施しているが記録がない
- 労働者への説明を怠った
これらはすべて「体制が整っていない」と評価され、更新審査で不許可につながります。
👉 関連:派遣事業更新と労働局対応ガイド
不許可を避けるためのチェックリスト
雇用安定措置の実務では、次の点を定期的に確認しておくと安心です。
- 3年ルールの対象者をリストアップしているか
- 派遣先に対して直接雇用依頼を行ったか(証拠保存)
- 拒否時に就業機会確保措置を講じたか
- 労働者に対して説明を行ったか
- 記録を3年以上保存しているか
👉 関連:派遣事業更新の実務フロー完全ガイド
雇用安定措置を徹底して更新審査を突破
派遣事業更新において、雇用安定措置は「派遣労働者の未来を守る仕組み」であると同時に、「事業者の更新合否を分ける基準」でもあります。
- 直接雇用依頼は必ず記録を残して行う
- 拒否された場合は就業機会確保措置を実施
- 記録と説明を怠らず、労働局に提示できる体制を整える
これらを徹底することで、不許可リスクを避け、安心して派遣事業を継続できます。