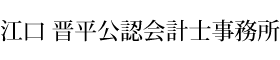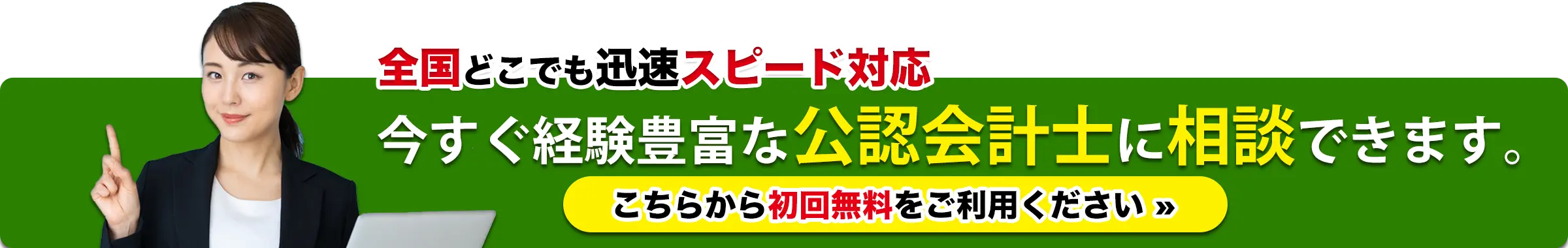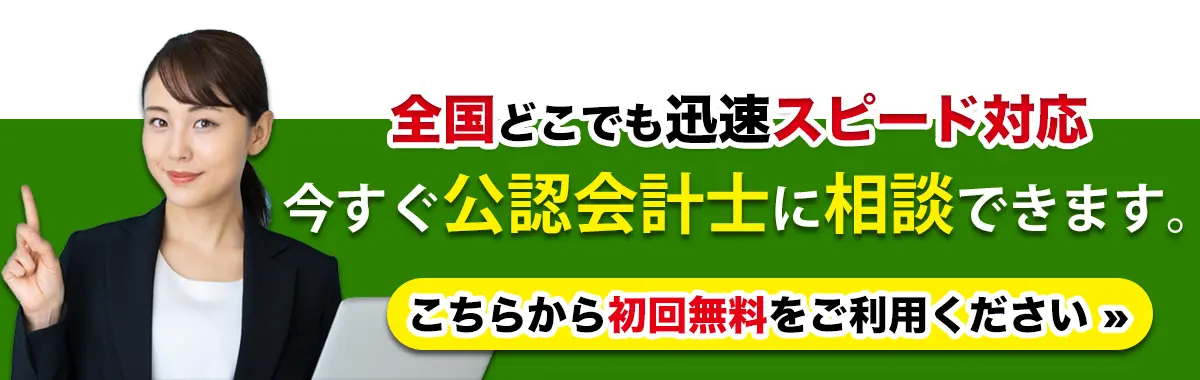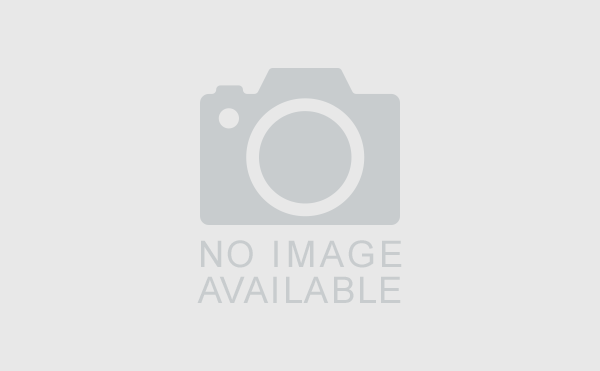職業紹介事業の許可とは?
職業紹介事業とは、求職者と求人企業を結び付け、雇用契約の成立を支援する事業です。
この事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要で、有料・無料にかかわらず必ず申請手続きが求められます。
無許可で行った場合は職業安定法違反となり、罰則や行政処分の対象となります。
したがって、人材紹介を始めたい場合は、必ず許可を取得することが第一歩です。
有料と無料の違い
職業紹介事業には「有料」と「無料」があります。
- 有料職業紹介: 求職者や求人企業から手数料を受け取る形態
- 無料職業紹介: 大学や自治体、NPOなどが無償で行う形態
どちらも許可制であり、申請の流れはほぼ同じですが、費用面などに違いがあります。
詳細は無料職業紹介事業の許可をご覧ください。
許可を取得するための要件
職業紹介事業の許可を得るためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 資産要件: 基準資産額500万円以上で債務超過でないこと → 資産要件の詳細
- 事務所要件: 独立区画を持ち、プライバシーを守れる面談スペースを設けること
- 体制要件: 職業紹介責任者を配置し、講習を修了していること
- 法令遵守: 過去に重大な法令違反がないこと
これらの要件を満たしていないと、申請は認められません。
申請の流れ
許可申請は次のステップで進められます。
- 資産・事務所・体制の整備
- 職業紹介責任者講習の受講
- 必要書類を準備(定款、登記事項証明書、決算書など)
- 労働局で事前相談
- 許可申請書を提出
- 審査(通常1〜2か月)
- 許可証の交付
申請窓口は管轄の労働局です。
必要書類
申請に必要となる代表的な書類は以下の通りです。
- 職業紹介事業許可申請書
- 登記事項証明書・定款
- 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)
- 資産証明書類(残高証明など)
- 事務所図面・賃貸借契約書
- 職業紹介責任者講習修了証
- 役員の履歴書・誓約書
不備があると申請が受理されないため、注意が必要です。
費用について
許可取得には最低限以下の費用がかかります。
- 登録免許税: 有料の場合9万円、無料の場合は免除
- 職業紹介責任者講習費用: 約1万円
加えて、
- 事務所整備費(内装や備品設置など)
- 資産要件を満たすための増資・借入費用
- 行政書士・社労士など専門家への依頼費用(任意)
費用の詳細は費用ページもご覧ください。
許可の有効期間と更新
許可は5年間有効で、継続する場合は更新が必要です。
更新時も資産・体制・事務所要件が審査され、帳簿の整備状況も確認されます。
詳しくは更新の解説をご確認ください。
よくある不備
申請でよく見られる不備は以下です。
- 資産要件を満たしていない
- 責任者講習修了証の不足
- 事務所要件の不備(独立性不足)
- 決算書と申請書の数字の不一致
これらは申請差し戻しや不許可につながるため注意が必要です。
許可を取得するメリット
許可を取得すると次のようなメリットがあります。
- 正式に人材紹介サービスを展開できる
- 求職者や企業から信頼を得られる
- 求人広告に許可番号を記載できる
- 派遣業より参入障壁が低い
事業開始のために不可欠な手続きです。
よくある質問(FAQ)
- Q. 許可取得にはどれくらいかかりますか?
- A. 通常1〜2か月程度ですが、不備があるとさらに時間がかかります。
- Q. 赤字決算でも許可は取れますか?
- A. 自己資本が基準を満たしていれば可能です。不足がある場合は増資や借入で改善します。
- Q. 有料と無料で申請方法は違いますか?
- A. 基本的な流れは同じですが、費用や必要書類に一部違いがあります。
関連ページ
あわせて以下の記事もご覧ください。
まとめ:職業紹介事業の許可は必須
職業紹介事業を始めるには厚生労働大臣の許可が欠かせません。
資産・体制・事務所の要件を満たし、必要書類を整えればスムーズに取得できます。
「無料だから不要」と誤解されがちですが、無料でも許可は必須です。
事前に十分な準備を行い、安心して人材紹介ビジネスをスタートさせましょう。